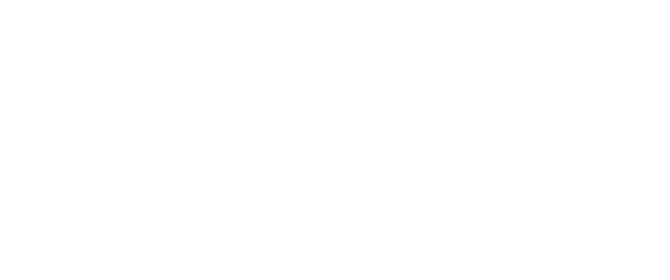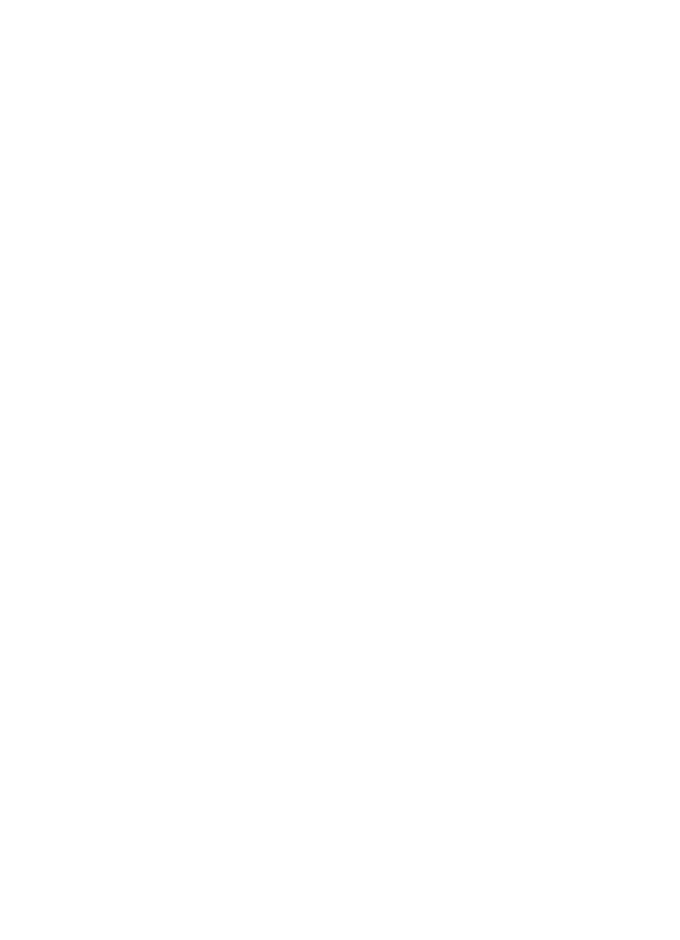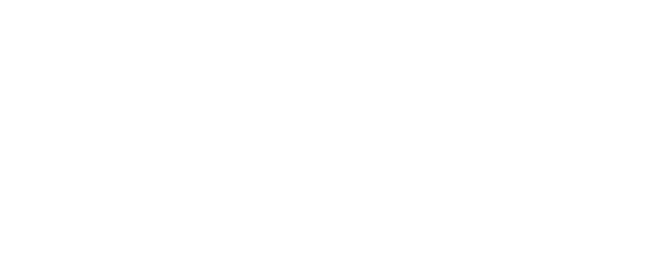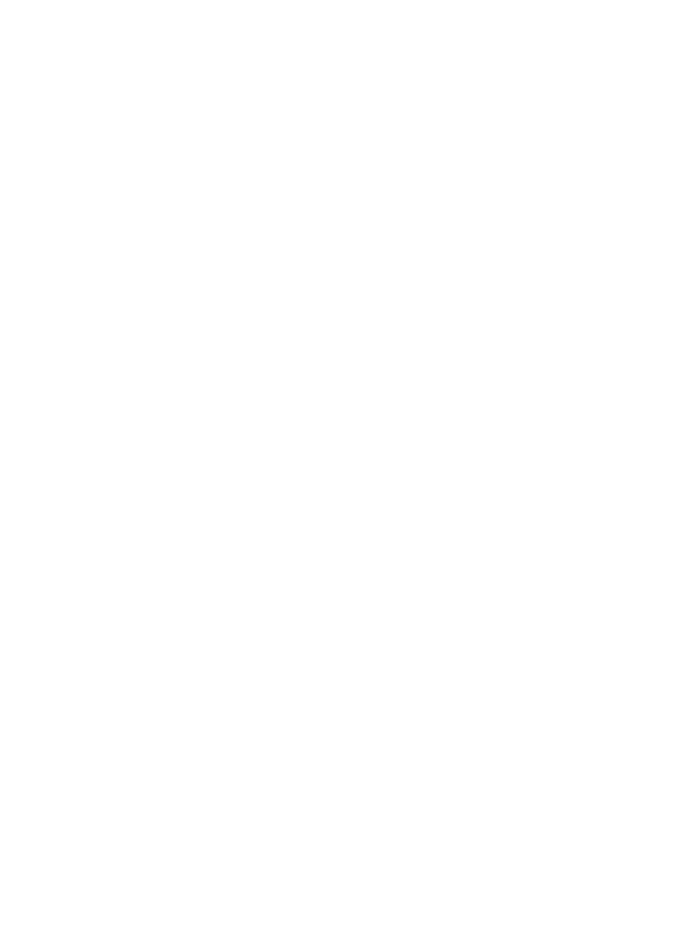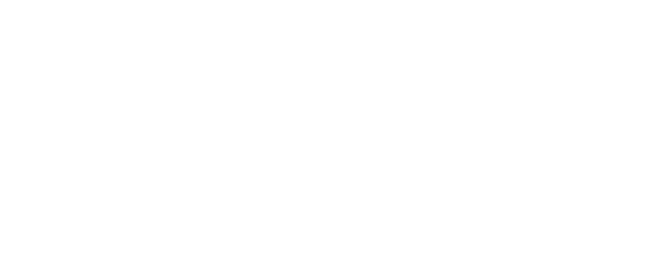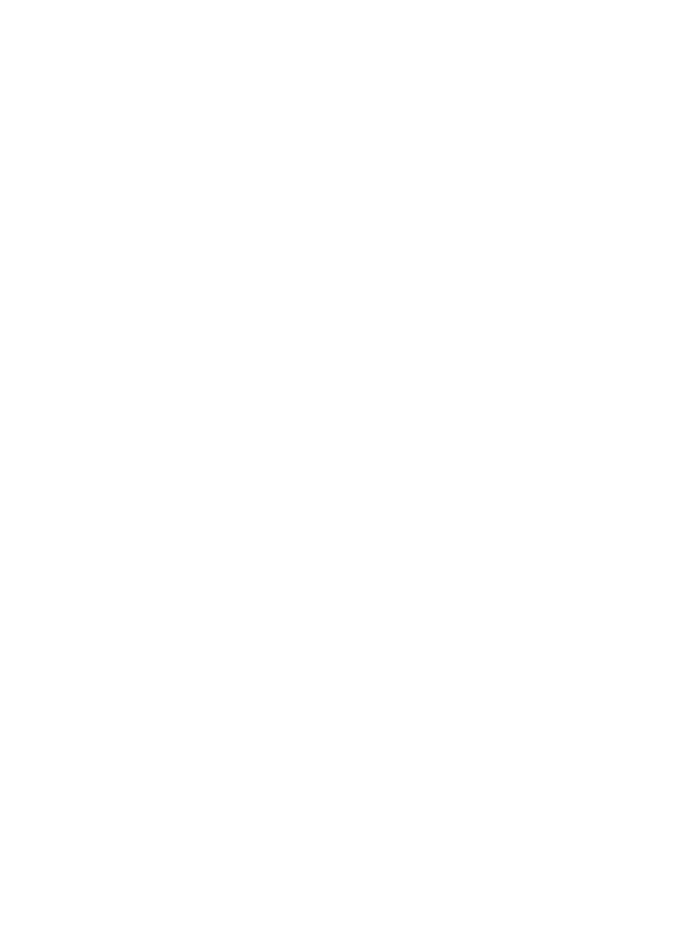コラム
Column
二十四節気を知る:季節の移ろいを感じる日本の暦
古来から日本人は、空や風の変化、鳥や花、虫たちの動きなど、自然の現象から季節の移り変わりを感じ取っていました。
太陽の動きを基準に一年を二十四の期間に分け、それぞれの季節の始まりや変化を教えてくれるのが、二十四節気という暦です。
日常でふと立ち止まり空を見上げてみたり、風や草木の香りをかいでみたりすることで、季節の変遷を実感できるかもしれません。
今回は、二十四節気の由来や二十四節気を取り入れた季節の楽しみ方についてご紹介します。
Contents
二十四節気の起源とその役割

二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、それぞれをさらに6つに分けたもの。
旧暦(太陰暦)において季節を表すために用いられていました。
約6世紀ごろに中国から伝来し、日本で用いられるようになったとされています。
平安時代に盛んだった文化の一つとして、短歌を思い浮かべる方も少なくないと思います。
奈良時代ごろから嗜まれ、平安時代には貴族間でかなり流行していた短歌では、心情や風景だけでなく、移り変わる四季の情景を繊細に描いていました。
また、日本では古くから神を奉る祭祀を、季節の変わり目などさまざまなタイミングで行っていました。
こうした日本の文化と二十四節気の相性の良さが、日本に定着した原因の一つかもしれませんね。
「二十四節気」そのものは聞きなれないかもしれませんが、日常的にときどき耳にする「立春」「夏至」「秋分」なども、二十四節気にあてはまります。
【二十四節気名とその時期】
| 季節 | 二十四節気名(読み方) | 月 | 新暦の日付 |
|---|---|---|---|
| 春 | 立春 (りっしゅん) | 1月中 | 2月4日頃 |
| 雨水 (うすい) | 1月下 | 2月19日頃 | |
| 啓蟄 (けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
| 春分 (しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |
| 清明 (せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |
| 穀雨 (こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
| 夏 | 立夏 (りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
| 小満 (しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
| 芒種 (ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |
| 夏至 (げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
| 小暑 (しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
| 大暑 (たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |
| 秋 | 立秋 (りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |
| 処暑 (しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
| 白露 (はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |
| 秋分 (しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |
| 寒露 (かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
| 霜降 (そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |
| 冬 | 立冬 (りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
| 小雪 (しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
| 大雪 (たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
| 冬至 (とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
| 小寒 (しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
| 大寒 (だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |
二十四節気の日付が固定されていないのは、二十四節気が太陽の動きを元に算出されるものであるためです。
二十四節気は地球から見た太陽の動き(または地球の公転周期)を24分割したもの。
地球から見た太陽の動き(または地球の公転周期)を24分割すると、およそ15日周期で二十四節気が変化する計算になります。
そのため「およそこれくらいだろう」という日付は決まっています。
ただ、15日周期はあくまでも目安であるため、およその日時は定まっていますが「毎年なん日が二十四節気の◯◯」と、明言はできないのです。
〈カレンダーの春分・秋分の日はどう決める?〉

二十四節気の日付が固定されていない、とお話しましたが、カレンダーには「春分」などの言葉が散見されます。
これは、祝日としての春分の日・秋分の日は国立天文台によって毎年計算され、前年の2月1日に決定されるルールであるためです。
前年の2月1日に国立天文台が、月食や日出入、国民の祝日や二十四節気についてのデータや要項をまとめた「暦要項(れきようこう)」を官報に掲載します。
これを機に、翌年の春分・秋分の日が確定するのです。
各節気の特徴と旬の食材
二十四節気は四季をさらに細かく分類することで、より繊細に季節を表しています。
その節気ごとの風景を、旬の食材とともに見ていきましょう。
【春の節気と旬の味覚】

| 二十四節気 | 特徴 | 旬の味覚 | 新暦の日付 |
| 立春(りっしゅん) | ・暦の上では春の始まり ・鶯の初鳴きが聞こえる ・朝はまだ冷えるものの、春の気配が感じられる | ・フキノトウ ・キウイ ・鰆(さわら) | 2月4日頃 |
| 雨水(うすい) | ・雪が雨へ ・積もった氷がゆるやかに溶け始める ・河口で白魚漁が始まる ・草木が芽吹くころ | ・菜花(なばな) ・いちご ・ワカサギ | 2月19日頃 |
| 啓蟄(けいちつ) | ・太陽のぬくもりに誘われ、虫が土から顔を出すころ ・桃の花がほころび始める | ・ワラビ ・デコポン ・鰊(にしん) | 3月5日頃 |
| 春分(しゅんぶん) | ・昼と夜の長さがほぼ等しくなる日 ・この日を境に、昼間の時間が少しずつ伸びていく ・鳥たちの巣作り、桜の開花など、春の深まりを感じるころ | ・新玉ねぎ ・オレンジ ・春大根 | 3月21日頃 |
| 清明(せいめい) | ・春がもっとも色づくころ ・草木の芽吹きが本格化、桜も満開に ・春雨が降ることも | ・春キャベツ ・グレープフルーツ ・鰹(かつお) | 4月5日頃 |
| 穀雨(こくう) | ・畑の緑がいっそう鮮やかに広がるころ ・上着がいらないほど汗ばむ日も ・春から初夏への橋渡しとなる節気 | ・さやえんどう ・びわ ・ヤリイカ | 4月20日頃 |
暦のうえで、春は「立春」から始まります。
冬至と春分の中間にあたる季節です。
立春ごろはまだ肌寒い日もありますが、ぬくもりのあるやわらかな日差しで、春の訪れを少しずつ感じられる時期でもあります。
春ごろに楽しめる食材として、独特の「苦み」や「香り」を持つものが多いのもこの時期です。
例えばセリ、フキノトウ、タラの芽などの山菜ですね。
これは、この季節だからこそ味わえる季節の食材です。
天ぷらや和物など、春の食材で食卓を彩ってみてはいかがでしょうか。
【夏の節気と旬の味覚】

| 二十四節気 | 特徴 | 旬の味覚 | 新暦の日付 |
| 立夏(りっか) | ・暦のうえで夏の始まり ・富士山の雪が溶け始めるころ ・田んぼでは苗代の準備が進む | ・たけのこ ・そら豆 ・夏みかん | 5月5日頃 |
| 小満(しょうまん) | ・草木が育ち、自然が活気づくころ ・新茶や山菜が出回り始める ・初鰹が旬、梅雨の気配も | ・さやえんどう ・メロン ・カレイ | 5月21日頃 |
| 芒種(ぼうしゅ) | ・麦など穀物の収穫が始まる ・衣替えの季節、街は夏の装いに ・鮎漁解禁、蛍や青梅も見られる | ・トマト ・あんず ・キス | 6月6日頃 |
| 夏至(げし) | ・昼がもっとも長くなる日 ・梅雨の中でも夏祭りが始まるころ ・川下りや鵜飼いが各地で開催 | ・キュウリ ・桃 ・アユ | 6月21日頃 |
| 小暑(しょうしょ) | ・梅雨が明け、夏本番へ ・ぶどうやゆずが青い実をつける ・蓮の花が咲き、暑中見舞いの時期 | ・トウモロコシ ・青りんご ・ハモ | 7月7日頃 |
| 大暑(たいしょ) | ・一年でもっとも暑いころ ・蝉が鳴き、花火大会や川開きが盛んに ・土用の鰻、夏野菜がおいしい季節 | ・ゴーヤ ・ぶどう ・アナゴ | 7月23日頃 |
暦のうえで、夏は「立夏」から始まります。
まだまだ本格的な夏日ではないため、過ごしやすい気候が多いころです。
日が経つごとに日差しが強くなり始め、気づけば蝉の声が遠くに聞こえるようになるでしょう。
夏至や小暑を迎えるころには、気温も湿度も高くなり、体も疲れがちに。
最近の研究では、紫外線が疲労の原因になり得るとも言われています。
紫外線の強まる夏日は特に気をつけた方が良いでしょう。

疲労感を感じがちな夏。
そのような時には、きゅうりやトマト、桃など水分の多い食材を取り入れるのがおすすめです。
さっぱり食べられるうえに、見た目も涼やかで、体の熱を逃してくれる頼もしい存在と言えるでしょう。
特にトマトは、紫外線による疲労感に対抗するために必要な成分(パントテン酸)を多く含んでいます。
ぜひ、今年の夏は積極的にトマトを食卓に並べてみてはいかがでしょうか?
【秋の節気と旬の味覚】

| 二十四節気 | 特徴 | 旬の味覚 | 新暦の日付 |
| 立秋(りっしゅう) | ・暦のうえで秋の始まり ・残暑が厳しく体力も落ちがち ・夕暮れにひぐらしが鳴き、秋の気配が漂うように | ・パプリカ ・すいか ・マスカット | 8月8日頃 |
| 処暑(しょしょ) | ・暑さがやわらぎ始めるころ ・穀物が実り、秋の草花が咲く ・涼しい風が時折吹き抜ける | ・オクラ ・ショウガ ・すだち | 8月23日頃 |
| 白露(はくろ) | ・草花に朝露が宿るころ ・空気がひんやりとし、秋の訪れを感じる ・台風の多い時期でもある | ・ナス ・梨 ・太刀魚(たちうお) | 9月8日頃 |
| 秋分(しゅうぶん) | ・昼夜の長さがほぼ等しくなる日 ・鰯雲が広がり、空は澄みわたる ・お彼岸の供養に訪れる穏やかな秋日和 | ・栗 ・いちじく ・鯖(さば) | 9月23日頃 |
| 寒露(かんろ) | ・朝晩に寒さを感じ始めるころ ・露が冷気にあたり、霜に変わることも ・水辺には渡り鳥が姿を見せ始める | ・チンゲンサイ ・柿 ・ししゃも | 10月8日頃 |
| 霜降(そうこう) | ・晩秋の澄んだ空に霜が降りる時季 ・紅葉が進み、火のぬくもりが恋しくなる ・山にはきのこが現れ、奈良では鹿の角切りも | ・サツマイモ ・りんご ・秋鮭 | 10月24日頃 |
「実りの秋」と呼ばれるほど、秋ごろは穀物や果物などの収穫が多くなる季節です。
サツマイモや栗、きのこに柿、どれも香り豊かで、素材本来の味わいが楽しめます。
立秋や処暑は、まだまだ夏ならではの重たい暑さが残っていますが、秋分あたりには夏の名残りもあまりなく、過ごしやすい気候となります。
過ごしやすい気候や、秋が旬となる豊富な食材が多いことが「食欲の秋」と呼ばれるゆえんなのだとか。
しかし、秋の楽しみ方はもちろん食べ物だけではありません。
例えば「天高く馬肥ゆる秋」との言葉があるように、秋は空が高く(雲が高い位置に見える)、澄みわたって見えることの多い季節です。
外出時に空を見上げて、季節の移り変わりを感じてみてはいかがでしょうか。
【冬の節気と旬の味覚】

| 二十四節気 | 特徴 | 旬の味覚 | 新暦の日付 |
| 立冬(りっとう) | ・暦のうえで冬の始まり ・初冠雪の知らせが届くころ ・木枯らしが吹いたあとに小春日和も訪れる | ・ゴボウ ・洋梨 ・牡蠣 | 11月7日頃 |
| 小雪(しょうせつ) | ・北風が強まり、落葉が舞う季節 ・時折、雪がちらつき始める ・みかんが色づき、炉開きの頃合い | ・ほうれん草 ・みかん ・ズワイガニ | 11月22日頃 |
| 大雪(たいせつ) | ・平地でも雪が降るように ・南天の赤い実が冬を知らせる ・冬将軍の到来、山々は雪化粧 | ・小松菜 ・レモン ・鱈(たら) | 12月7日頃 |
| 冬至(とうじ) | ・一年でもっとも昼が短く夜が長い日 ・かぼちゃや小豆粥で無病息災を願う ・ゆず湯に浸かり、体を温める風習も | ・かぼちゃ ・柚子 ・金目鯛(きんめだい) | 12月21日頃 |
| 小寒(しょうかん) | ・「寒の入り」で本格的な寒さに ・出初式や七草粥で新年の健康を祈る ・北国では連日の雪模様が続く | ・かぶ ・金柑 ・河豚(ふぐ) | 1月5日頃 |
| 大寒(だいかん) | ・一年でもっとも寒さが厳しい時季 ・二十日正月や天神様へのお参りの風習あり ・冷え込みが強まり、凍てつく朝が日常に | ・春菊 ・ポンカン ・鰤(ぶり) | 1月21日頃 |
暦のうえで冬が始まるのは「立冬」。
山頂部に雪が積もり、白く見える状態を「冠雪」と言いますが、初の冠雪(初冠雪)が観測されるのはだいたい立冬のころだとされています。
寒さの厳しくなる冬至や大寒のころ、多くのご家庭で活躍するのは鍋ものではないでしょうか。
鍋を作る際には、ニンジンや大根、ゴボウなどの根菜類が特におすすめです。
根菜類は体を内側から温めてくれる優れもの。
特に味噌やショウガを使った汁物と合わせると、体の芯からぽかぽかしてきます。

食材以外の話をすると、冬場はほかの季節よりも空気中の水分やちりなどが少なく、空気がとても澄んでいるのが特徴です。
気温の低さも影響しているため、本格的な寒さが訪れる小寒あたりから清々しい空気を感じることが多くなるかもしれませんね。
空気が澄んでいると遠くの景色がよりはっきり見えるため、夜空の星々もきれいにみることができます。
冷たく澄んだ空気をいっぱいに吸い込んでみるのもおすすめです。
今年の冬はベランダから夜空を眺めたり、静かなひとときを楽しんだりしてみてはいかがでしょうか。
暦と暮らし:二十四節気の活用法

現代では、季節はカレンダーや天気予報で確認できますし、野菜や果物なども通年販売されています。
とても便利なものですが、時には季節に寄り添った食事や生活を楽しんでみるのも良いかもしれません。
この章では二十四節気を生活の中に取り入れる方法をご紹介します。
【旬の食材を使った料理で食卓をより豊かに】

通年販売されているとはいえ、その節気に合った旬の食材はより栄養価も高く、価格も安定しやすいという利点があります。
立春には山菜を用いた天ぷら、大寒には鰤と春菊を用いた鍋物など、季節に合わせた料理を食卓に並べることで、より季節を楽しむことができるでしょう。
【季節の伝統行事や伝統文化の再発見】
二十四節気には、古くから地域に根ざした伝統行事が多く残っています。
例えば、秋分の日におはぎを食べたり、冬至にはゆず湯を楽しんだりなど。
こうした風習を取り入れることで、家族や地域とのつながりも自然と深まっていくかもしれませんね。
関連記事:お彼岸にお供えする食べ物は何が適切?なぜおはぎとぼたもちが定番なのかも解説
日本ならではの四季を通じ、ゆとりのある生活を

今回は二十四節気についてご紹介しました。
現代の暮らしにおいて、季節の変化を感じにくくなってきているのも事実でしょう。
実際、九州地方では年平均気温が100年あたりおよそ1.7℃の割合で上昇している状況が観測されているそうです。
こうした変化が、自然との距離を少しずつ広げてしまっているのかもしれません。
だからこそ、今あらためて大切にしたいのは、自然の小さな変化に耳を傾ける「心のゆとり」ではないでしょうか。
変わりゆく気候の中でも、季節を感じ、暮らしに生かしていく。
季節ごとの気配や風の香り、光のやわらかさを感じ取ることは、自分らしいペースで自分らしい暮らしを整えるためのヒントかもしれませんね。