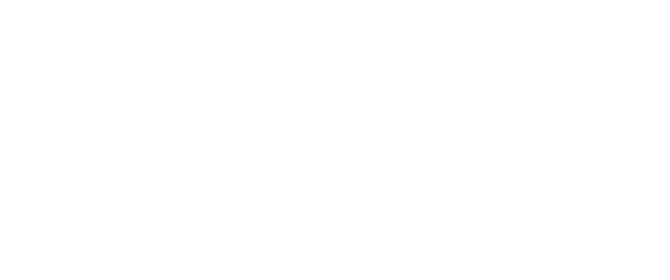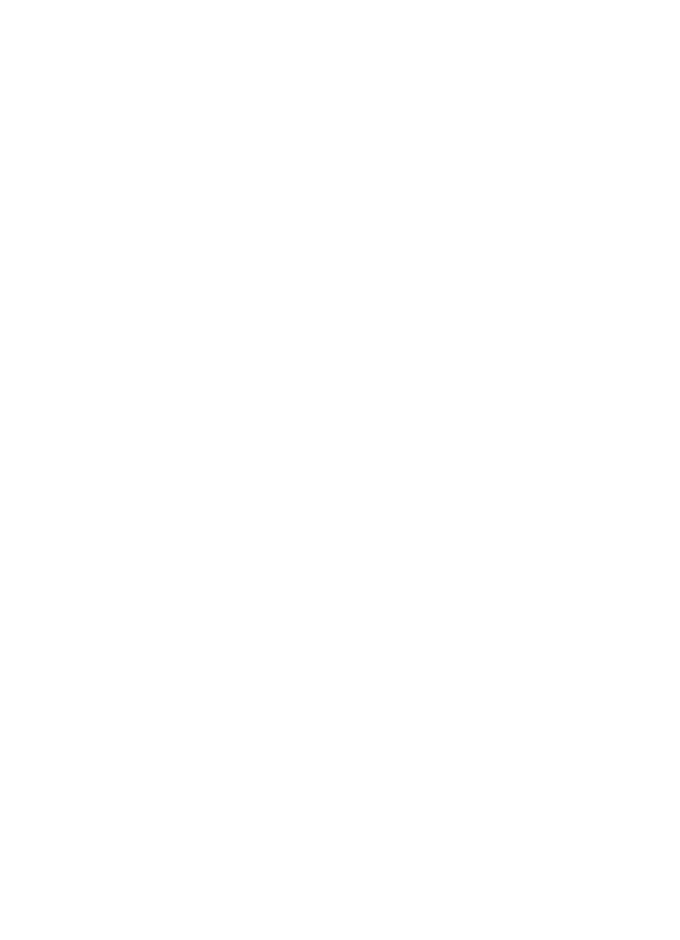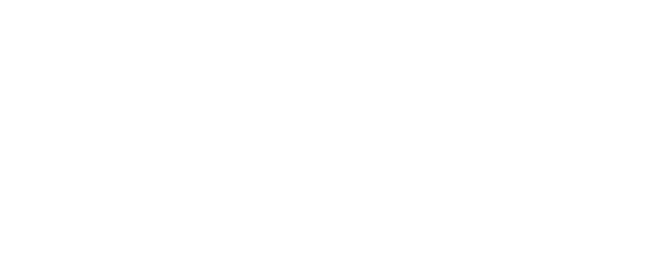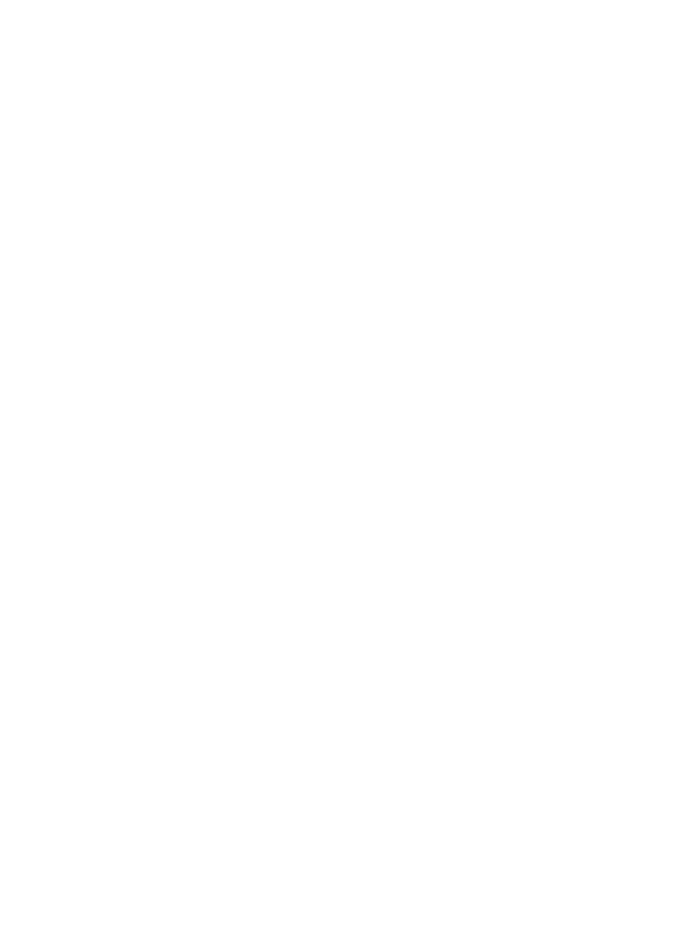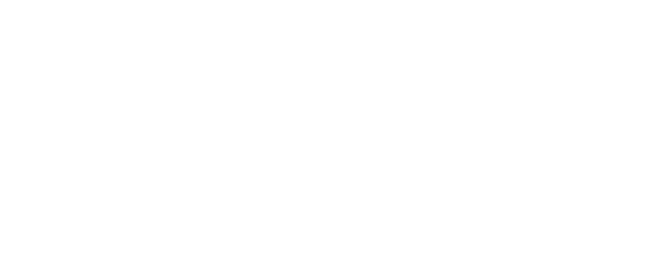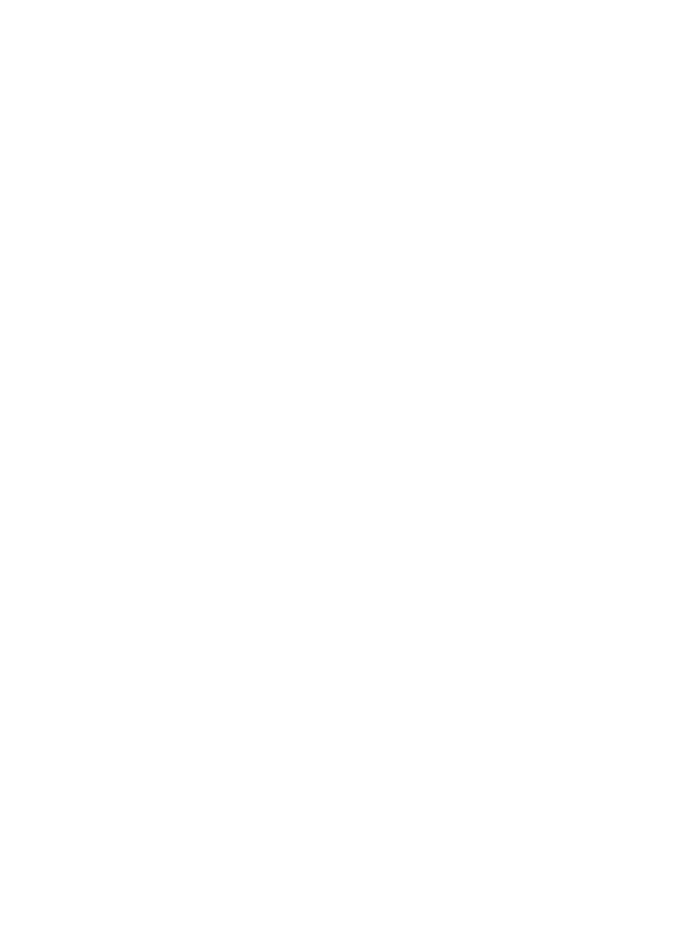コラム
Column
和菓子の名前が入った慣用句やことわざ、いくつご存じですか?
日本の言葉には、和菓子の名前を使った慣用句やことわざが数多くあります。
普段何気なく使っている言葉の中にも、実は和菓子に関する言葉が隠れているかもしれません。
これらの表現には、日本の文化や生活習慣、思想が反映されているものが多く、それぞれにおもしろい意味が込められています。
今回は「饅頭」「団子」「羊羹」「ぼたもち」「せんべい」「お茶」にまつわる慣用句やことわざを紹介しながら、その背景にある意味や由来を解説していきます。
Contents
そもそも慣用句とは?ことわざとの違いは?
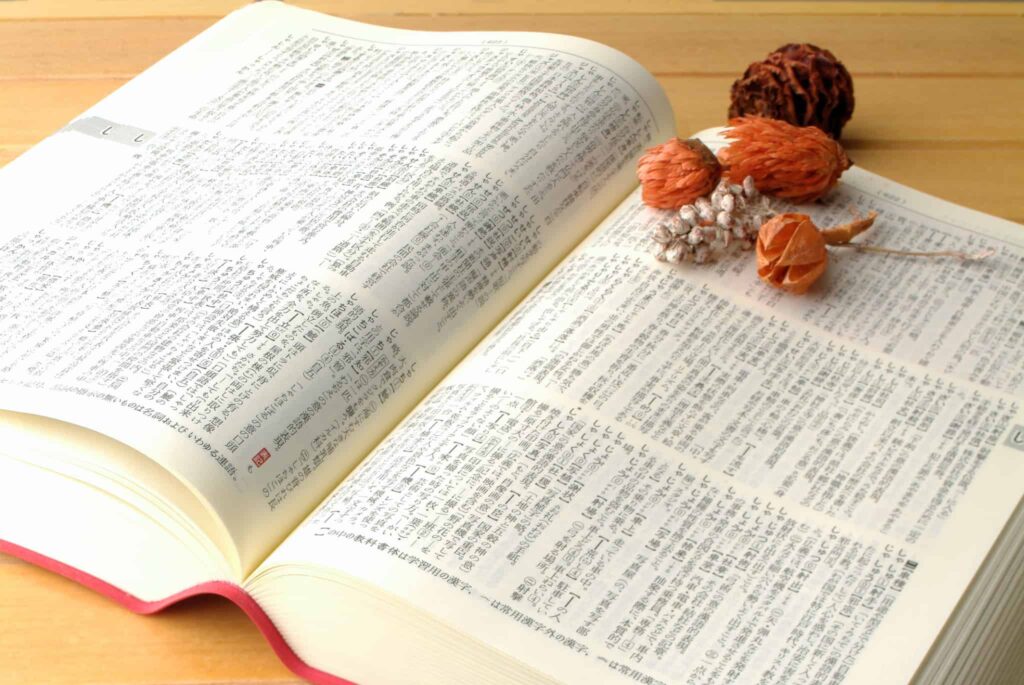
「慣用句」と「ことわざ」は似たような表現ですが、異なる特徴があります。
慣用句とは、複数の言葉が決まった形で組み合わさり、一つの意味を持つ表現のことを指します。
例えば「顔が広い」という表現は「顔」と「広い」の2つの言葉が組み合わさった慣用句です。
この言葉は実際に顔の大きさを指すのではなく「人脈が広い」という意味で使われますね。
一方ことわざは、人生の教訓や経験、知識などを含む簡潔な言葉のこと。
例えば「石の上にも3年」ということわざは、辛抱していればいつかは成功することを「冷たい石の上でも、長年座ることでいつかは温まる」ことに置き換えて表現しています。
慣用句もことわざも、どちらも日常会話で使われることが多く、日本語の豊かさを感じられる表現と言えるでしょう。
饅頭(まんじゅう)に関する慣用句・ことわざ

この章では「饅頭」の言葉が含まれる慣用句・ことわざについて紹介します。
【ことわざ:心中(しんじゅう)より饅頭】
「心中より饅頭」とは、見栄や体裁よりも実益の方を優先することを表した言葉です。
「心中」にはいくつかの意味があり、その中で「人への義理を守る」という意味があることをご存じでしょうか?
今回のことわざにおける「心中」というワードは「義理」として用いられています。
「義理のために命を捨てるよりも、饅頭(おいしいもの)で腹を満たした方が良い」という考えから、こうしたことわざが生まれました。
【ことわざ:雪隠(せっちん)で饅頭】
「雪隠で饅頭」とは、こっそりと何かを楽しむことを表したことわざです。
空腹を満たすためには、場所を選ばないという意味合いもあり、そこから転じて、どんな場所でも自分の欲求を満たすという意味合いで使われる場合もあります。
「雪隠」とは今で言うトイレのこと。
トイレのような人目につかない場所でこっそり饅頭を食べる、という状況から生まれた表現です。
実際の状況をイメージすると分かりやすいですが、このことわざには「隠れて自分だけいい思いをする」という意味合いと「おいしいものはどこで食べてもおいしい」という意味合いに分かれます。
そのため、実際に使用する際には少しややこしいかもしれませんね。
〈饅頭とは〉

「心中より饅頭」や「雪隠で饅頭」などの表現に登場する饅頭とは、小麦粉や米粉を使った生地で餡を包み、蒸した和菓子です。
日本へは中国から伝わり、時代とともにさまざまな種類が生まれました。
伝来した当時は野菜や肉、塩味の小豆餡を使用した饅頭が多かったようですが、砂糖が普及するにつれて、甘い和菓子としても広い地域へ広まったとされています。
庶民にも広く親しまれるようになり「酒饅頭」「温泉饅頭」など、時代の流れとともに地域ごとに特色ある饅頭が作られるようになりました。
団子に関する慣用句・ことわざ

この章では「団子」の言葉が含まれる慣用句・ことわざについて紹介します。
【ことわざ:花より団子】
「花より団子」は、見た目よりも実益を求めることを表すことわざです。
食べられない花より、実際に食べて腹に溜まる団子の方がありがたいという考え方から生まれました。
お花見などの席でも、よく耳にするのではないでしょうか。
転じて、華やかな装飾や表面的な魅力よりも、実際に役立つものや価値のあるものを重視する姿勢を示す言葉としても使用されるため、さまざまな場面で耳にすることわざと言えます。
【慣用句:団子レース】
「団子レース」とは、実力が拮抗していてなかなか優劣がつかない競争のことを表現した慣用句です。
団子は何かを一塊にしたものを表すこともあるため、そうした意味合いからこの言葉が生まれたのだと考えられます。
【ことわざ:案じるより団子汁】

「案じるより団子汁」とは、心配するより気楽に待っておこう、という助言を表したことわざです。
「案ずるより産むが易し(=物事は心配するより、実行に移してみると案外楽であること)」をもじった言葉とされています。
それだけでなく「案じる」は「餡汁」の語呂合わせでもあります。
つまり、団子の入っていない餡汁よりも、団子入りの汁の方が良い、というシャレなわけですね。
ちなみにここで言う「団子汁」とは、いわゆるぜんざいのこと。
熊本に「団子汁(だごじる)」という郷土料理がありますが、これとは別物です。
【ことわざ:団子は串に刺した方がいい】
「団子はくしに刺した方がいい」は、何事もその物事に応じた適切な対応をした方が良いことを表すことわざです。
団子は、バラバラの状態よりも串に刺すことで食べやすくなります。
そこから転じて、このことわざが生まれたとされています。
その時々で、もっとも合理的で効率の良い方法を選択することを表す言葉なので、ビジネスシーンなどで使えるかもしれませんね。
〈団子とは〉

「花より団子」や「団子レース」といったことわざに登場する団子とは、お米などの穀物を粉末にしたものを丸め、茹でたものです。
茹でたあとで焼いたものも見られます。
味付けは醤油や味噌、あんこ、きなこなどさまざまなバリエーションがあり、多くの人に愛される食べ物の一つと言えるでしょう。
昔から縁起の良い食べ物とされていて「花見団子」や「月見団子」など、季節の行事とも深く関わっています。
関連記事:月見の意味を解説。なぜ月見のイメージが団子やススキなのか知っていますか?
羊羹(ようかん)に関する慣用句・ことわざ

今回ご紹介することわざは「羊羹」の言葉は用いていませんが、羊羹と少し関係のある言葉なのでご紹介します。
【ことわざ:羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く】
「羹に懲りて膾を吹く」とは、一度失敗した人が過剰に警戒してしまう様子を表すことわざです。
羹とは肉や野菜を入れた熱いお吸い物のこと。
熱い汁物で火傷した人が、冷たい酢の物(膾=酢の物)まで吹いて、冷まそうとする様子から転じて生まれたことわざだと言われています。
小豆と寒天で作られた羊羹と、熱い汁物を示す「羹」。
全然違う食べ物なのに、なぜ同じ漢字が使われているのか、疑問を抱いた方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、日本へ羊羹が伝来した当時は、羊の肉やゼラチンが入った汁物を「羊羹」としていたのです。
なぜ、汁物から今のような形になったのでしょうか?
羊羹の詳細については、下記の関連記事をご覧ください。
関連記事:年表で見る和菓子の歴史
〈羊羹とは〉
「羹に懲りて膾を吹く」ということわざに出てくる「羹(あつもの)」は、熱い汁物を指しますが、ここで関連する羊羹もまた、日本の和菓子として広く知られています。
羊羹は小豆に寒天や砂糖を練り合わせ、煮詰めたり蒸したりすることで作られる和菓子のこと。
夏の風物詩として人気の高い水羊羹は、煮詰めずに作ることで従来の羊羹よりも水分量が多いのが特徴です。
ぼたもちに関する慣用句・ことわざ

ぼたもちは、日本人にとってなじみ深い和菓子の一つです。
特に、お彼岸に食べる風習があることから、昔から多くの人に親しまれてきました。
そのため、ことわざや慣用句の中にも、ぼたもちを使った表現がいくつか存在します。
【ことわざ:開いた口に(へ)ぼたもち】
「開いた口にぼたもち」とは、努力することなく思いがけない幸運が舞い込んでくることを意味したことわざです。
何もせずに口を開けているだけで、おいしいぼたもちが飛び込んでくる、という情景が由来です。
今では考えられないことですが、砂糖は昔とても貴重なものとされていました。
そのため、当時の人にとって砂糖をふんだんに使用したぼたもちは幸運の象徴であったのだとか。
おそらくはこれを理由として「思いがけないところから幸運が舞い込んでくる」ことを表すことわざに、ぼたもちが使用される例がいくつか見られます。
次に紹介する「棚からぼたもち」も、その例です。
【ことわざ:棚からぼたもち】
「棚からぼたもち」は、「開いた口にぼたもち」と同様に、予期せぬ幸運が訪れることを表します。
「棚ぼた」と略して使用されることも多い印象ですね。
「開いた口にぼたもち」同様に、努力をせず、思いがけず得た幸運に対して使用されることわざです。
例えば、徒競走などにおいて実力で1位を獲得した際に「棚ぼたで1位を取った」とは言えません。
ほかの参加者が転んだり、欠場したりなど、不可抗力で1位を獲得した場合であれば、まさに「棚ぼた」と言えるでしょう。
【ことわざ:夜食過ぎてのぼたもち】
「夜食過ぎてのぼたもち」とは、必要な時を過ぎてから物事が手に入っても、すでに役に立たず、ありがたみや価値が下がることを意味することわざです。
言葉のとおり、夜食の時間が過ぎてからぼたもちをもらっても、すでにお腹が満たされていてうれしくない……、という場面から生じたことわざです。
例えば、試験が終わったあとに参考書をもらったり、必要な時期を過ぎてからアドバイスを受けたりするような場面にあてはまります。
〈ぼたもちとは〉

「開いた口にぼたもち」や「棚からぼたもち」といった表現に登場するぼたもちとは、もち米やうるち米を炊いて軽くつぶし、甘い小豆餡で包んだ和菓子で、お彼岸の定番として長年愛されています。
ぼたもちの「ぼた」とは牡丹(ぼたん)を表しており、昔は主にこしあんが使用され、ぼたんを模した丸い形をしていたとされています。
ぼたもちと似た食べ物で「おはぎ」がありますが、これらの違いや発祥については諸説あります。
詳細は、下記の関連記事をご覧ください。
関連記事:お彼岸にお供えする食べ物は何が適切?なぜおはぎとぼたもちが定番なのかも解説
せんべいに関する慣用句・ことわざ

せんべいは、米を原料とした日本の伝統的なお菓子で、パリッとした食感が特徴です。
このせんべいを使ったことわざの一つに「鬼にせんべい」という表現があります。
【ことわざ:鬼にせんべい】
「鬼にせんべい」とは、たちまち食い尽くしてしまうことを表すことわざです。
また、造作なくやりあげてしまうことを表すことわざとしても使用されます。
鬼にとっては、せんべいを食べることなど造作もないというイメージでしょうか?
たしかに、とても固いせんべいだと人によっては食べるのも難儀してしまいます。
そう考えると「造作なくやりあげてしまう」ことを表すことわざとして、まさにぴったりな表現と感じられますね。
〈せんべいとは〉

「鬼にせんべい」ということわざに登場するせんべいとは、米粉や小麦粉を練り、薄く引き伸ばしたものを焼いた日本の伝統的なお菓子です。
日本では、うるち米で作ったものをせんべいと呼んでおり、もち米を使用したものを「おかき」や「あられ」と呼びます。
瓦のように固いものから、ふんわりとしたソフトせんべいまで、多種多様なせんべいがあります。
お茶に関する慣用句・ことわざ

日本の文化と深く結びついているお茶には、多くの慣用句やことわざが存在します。
【慣用句:お茶を濁す】
「お茶を濁す」とは、適当な言葉や行動でその場を取り繕い、ごまかすことを意味します。
このことわざで使用される「お茶」とは、抹茶のこと。
茶道は今のように一般的に広まった文化ではありませんでした。
茶道を知らない人が、プロのように抹茶を点てることは難しいとされています。
茶道をよく知らない一般人は見よう見まねで茶碗の中を掻き回し、それらしくお茶を濁らせることで、その場を取り繕ったのだとか。
このことから転じ、生まれたことわざとされています。
【慣用句:お茶の子(お茶の子さいさい)】
「お茶の子」とは「簡単なこと」という意味で使われます。
本来お茶の子という言葉はお茶菓子の意味です。
お茶菓子(=お茶の子)は腹に溜まらない、ということから「たやすいこと」を表す言葉として使用されるようになったとされています。
ただ、よく聞くのは「お茶の子さいさい」という慣用句ではないでしょうか。
この慣用句は「お茶の子」に囃子言葉が合わさったものとされています。
囃子言葉とは、歌詞の字足らずを埋めて拍子を調節するために挿入された短い言葉のこと。
もともと、囃子言葉として「のんこさいさい」という言葉があり、お茶の子をもじって「お茶の子さいさい」という形になったと言われています。
【慣用句:茶に酔うたよう(ふり)】
「茶に酔うたよう(ふり)」とは、知っているのに知らないふりをすることを表した慣用句です。
本来、お茶では酔うことはありませんが、お茶を飲んで酔ったように見せかけることから転じて、上記の意味で使用されるようになりました。
【ことわざ:茶腹(ちゃばら)も一時(いっとき)】
「茶腹も一時」とは、少しのものでも一時的な助けにはなることを表したことわざです。
お茶を飲むことで、一時的に空腹を紛らわせることから転じて生まれたとされています。
「たったの一時しのぎにしかならないのか」というネガティブな意味合いでは使われないため、使用する際は注意が必要です。
〈お茶とは〉

「お茶を濁す」や「茶腹も一とき」といった表現に登場する「お茶」という言葉は、現代においてとても広い意味で使われます。
「お茶にしようか」と言葉をかけられた場合、テーブルに並ぶのは緑茶の可能性もありますし、紅茶やコーヒーの可能性も考えられるでしょう。
一般にお茶と言うと、現代においては乾燥させた植物の葉などをお湯や水で抽出した飲料の総称として、広く認識されています。
関連記事:緑茶と抹茶、何が違う?スイーツに緑茶ではなく抹茶が使われる理由も解説
ことわざに息づく和菓子の文化

和菓子の名前が入った慣用句やことわざには、それぞれの時代の人々の暮らしや考え方が反映されています。
食文化と日本語の関係は深く、言葉を通じて昔の人々の価値観を知ることができるかもしれません。
普段使っている言葉の中に、まだ知らない「和菓子」にまつわる表現が隠れていないか、探してみるのも面白いですね。